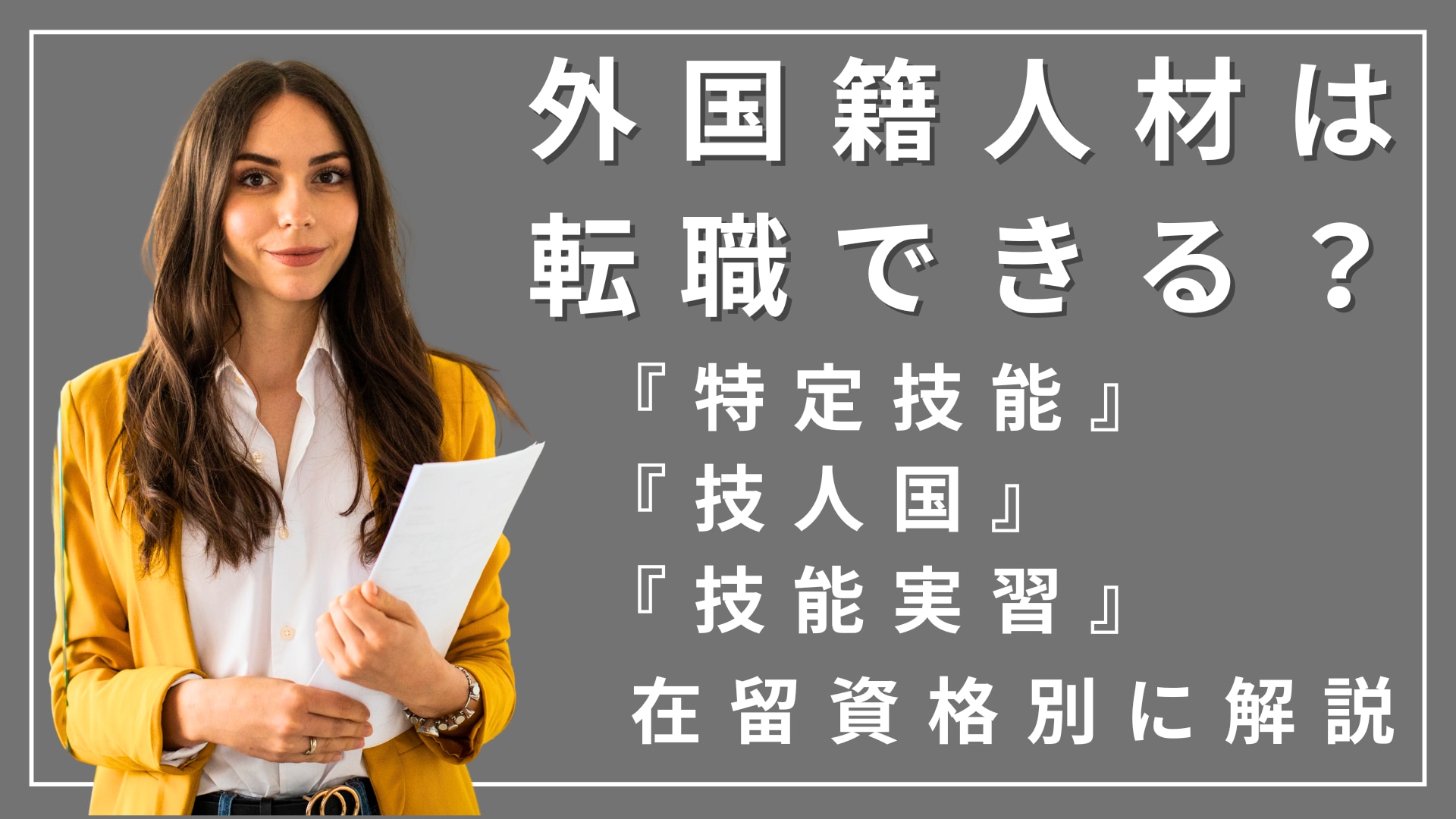
外国籍人材は転職できるの?在留資格ごとの要件と企業が知っておくべきこと
外国籍人材の採用・定着を考える企業の皆様にとって、「長く自社で働いてもらえるか」は極めて重要な課題です。特に「外国籍人材は自由に転職できるのか?」という問いは、在留資格によってルールが大きく異なるため、採用戦略を左右するポイントとなります。
本コラムでは、現在日本で就労する外国籍人材の主要な在留資格である「特定技能」「技術・人文知識・国際業務(技人国)」「技能実習」の3つに焦点を当てます。それぞれの転職の可否と厳格な要件、受け入れ企業が知っておくべき手続きや注意点、そして優秀な人材に長く定着してもらうためのポイントを具体的に解説します。
在留資格ごとの転職の可否
外国籍人材の転職(所属機関の変更)は、在留資格の種類によって大きく異なります。
1. 特定技能
転職はできる
ただし、転職が可能となるにはいくつかの要件を満たした場合に限ります。
2. 技術・人文知識・国際業務(技人国)
転職はできる
新しい仕事内容が在留資格の活動範囲(専門性)に該当することが必要。
3. 技能実習
転職はできない
制度上、原則として転職が認められていません。しかし、制度の目的を外れるような不当な状況下などは、例外的に転職(転籍)が認められます。
育成就労制度では転職ができるようになる
技能実習に代わる外国籍人材の新たな受け入れ制度「育成就労」が2027年度に開始予定です。育成就労制度では本人の意向による転職(転籍)が条件付きで認められ、就業する分野によって転籍制限期間が異なる仕様になる見込みです。(2025年10月現在)
※2025年9月に開催されたオンラインセミナーでは、育成就労について解説しております。是非、レポート記事をチェックしてください。
特定技能人材が転職するために必要な行動や手続き
特定技能は、日本の労働力不足を補うために創設された在留資格であり、引き続き日本で働いてもらえるので、原則として転職が可能です。
1. 特定技能人材(外国人本人)がすべきこと
転職先の選定
転職先が現職と同一分野・業務区分であること、または技能水準の共通性が確認されている分野であることを確認する。異なる分野の場合は、改めて評価試験に合格する必要がある。在留資格の要件を満たさない転職は不可。
雇用契約の締結
新しい受け入れ企業と特定技能雇用契約を締結し、契約書を受け取る。日本人と同等以上の報酬・待遇が必須。
在留資格の申請
地方出入国在留管理局へ「在留資格変更許可申請」または「在留期間更新許可申請」を行う。新しい企業から提供された書類一式を添付する。
届出の実施
旧受け入れ企業を離職したこと、および新受け入れ企業との契約を締結したことを、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る。届出を怠ると、在留資格の取り消し対象となる可能性がある。
2. 旧受入れ企業がすべきこと
契約終了の届出
外国人との雇用契約を終了した日から14日以内に、出入国在留管理庁に届け出る。「特定技能雇用契約の終了に関する届出」をオンラインまたは書面で提出。
生活・業務支援の終了
策定・実施していた支援計画を終了する。転職先の企業が新しい支援計画を引き継ぐため、支援の記録を整理する。
雇用保険等の手続き
雇用保険、社会保険など、日本人従業員の退職時と同様の公的機関への手続きを行う。ハローワークへの「外国人雇用状況の届出」も忘れずに。
3. 新受入れ企業がすべきこと
雇用契約の締結
特定技能人材と雇用契約を結び、日本人と同等以上の報酬・待遇を定める。労働条件通知書や雇用契約書を作成する。
支援計画の策定・実施
外国人が日本で安定して生活できるよう、10項目の支援計画(生活オリエンテーション、相談・苦情対応など)を策定する。支援は自社で実施するか、登録支援機関に委託する。
必要書類の作成・提供
在留資格申請に必要な企業の適格性を示す書類一式(雇用条件書、支援計画書、誓約書など)を漏れなく作成し、本人に提供する。書類は複雑なため、行政書士や登録支援機関の活用が一般的。
受入れ後の届出
特定技能人材を雇用した日から14日以内に、出入国在留管理庁に届け出る。
※登録支援機関については、過去掲載コラムで解説しております。
技術・人文知識・国際業務(技人国)人材が転職するために必要な行動や手続き
技人国ビザは、専門的な知識や技術、国際的な感覚を活かした業務に従事するための在留資格です。転職は可能ですが、仕事内容の専門性が重要です。
1. 技人国人材(外国人本人)がすべきこと
転職先の選定
転職先の業務が、本人の大学・専門学校での専攻や、これまでの職務経験に由来する専門性と合致していることを確認する。業務内容が単純作業に変わる転職は認められません。
雇用契約の締結
新しい受け入れ企業と雇用契約を結び、職務内容や期間を明確にする。報酬額は日本人と同等以上が原則。
在留資格の申請
地方出入国在留管理局へ「就労資格証明書交付申請」(任意)または「在留資格変更許可申請・更新申請」を行う。就労資格証明書を取得しておくと、企業側・本人側の安心感が高まります。
届出の実施
旧受け入れ企業を離職したこと、および新受け入れ企業との契約を締結したことを、14日以内に出入国在留管理庁へ届け出る。届出は本人の義務です。
2. 旧受入れ企業がすべきこと
契約終了の届出
外国人との雇用契約を終了した日から14日以内に、出入国在留管理庁に届け出る。届出を怠ると、企業の信用に影響する可能性があります。
雇用保険等の手続き
雇用保険、社会保険など、日本人従業員の退職時と同様の公的機関への手続きを行う。「外国人雇用状況の届出」もハローワークへ提出します。
3. 新受入れ企業がすべきこと
業務内容の確認と証明
採用する外国人の学歴・職務経歴と、採用後の業務内容が論理的に結びついていることを確認し、証明資料を作成する。業務内容が専門的であることを客観的に説明できるかが重要です。
必要書類の作成・提供
在留資格申請に必要な企業の適格性を示す書類一式(雇用契約書、会社の登記事項証明書、事業内容を説明する資料など)を本人に提供する。
受入れ後の届出
外国人を雇用した日から14日以内に、出入国在留管理庁に届け出る。その後の定期的な届出義務はありません。
技能実習生の転職が認められるケース
技能実習制度は、開発途上地域等への技能移転を目的としており、「転職の自由」は原則ありません。しかし、制度の目的を外れるような不当な状況下などにおいては、例外的に転職(転籍)が認められます。
1. やむを得ない事情
企業の倒産、事業の廃止、実習実施機関側による人権侵害(暴行、ハラスメント、賃金不払いなど)といった、技能実習を継続することが不可能または不適当な特別な事情がある場合に限られます。
2. 技能実習3号への移行
2号修了後、より高度な実習を行うために、別の企業へ移行(転籍)が認められる場合があります。
3. 特定技能への移行
技能実習2号を良好に修了し、特定技能の要件(主に分野)を満たせば、特定技能1号への在留資格変更を伴う転職が可能です。
技能実習生を例外的に転籍によって受け入れる企業は、転籍元の企業・監理団体、転籍先の企業・監理団体、そして機構(外国人技能実習機構)と出入国在留管理庁が関わる複雑な手続きを行う必要となります。特に、やむを得ない事情による転籍の場合は、個別の状況に応じて対応が異なります。
転職の注意点やリスク
外国籍人材の転職には、企業側も本人側にもいくつかの注意点やリスクが存在します。
1. 在留資格の空白期間と不法就労のリスク
外国人材が自己都合で退職し、次の会社へ転職する際、新しい在留資格の許可が下りるまでの期間は、原則として新しい会社で就労できません。許可までに1〜3ヶ月程度かかることが多く、この期間に働かせてしまうと、企業も外国人本人も不法就労となる重大なリスクを負います。採用内定後、在留資格変更(または更新)許可の通知が下りるまでは、いかなる業務にも就かせないよう、企業の徹底した管理が必要です。
また、在留資格の有効期限が切れてから、新しい在留資格が付与されるまでの期間を【空白期間】と呼びます。この期間中に日本国内で就労すると、在留資格に基づかない活動として不法就労とみなされる可能性があります。数日であっても、在留資格によって更新中や変更中の証明書(受領票)がないまま働くとリスクが高まり危険です。
不法就労とみなされる主なケースは次の3つです。
1. 在留期限満了後も日本に滞在して働いた場合
2. 在留資格変更/更新申請をせずに就労した場合
3.資格外活動の許可を受けずに就労した場合
※例)留学生・家族滞在など、就労が原則認められない資格で働いた、など
これらはいずれも入管法第19条・第70条に違反し、雇用主にも不法就労助長罪が問われる可能性があります。
空白期間(技能実習、特定技能)のリスク
技能実習修了後、特定技能への切り替えに時間がかかるケースが多く、COE(在留資格認定証明書)発行前や在留資格変更前に就労を始めると不法就労となります。在留カード裏面の有効期限や申請中の受領票を確認し、契約開始日は在留資格変更許可日以降に設定します。
空白期間(技人国)のリスク
会社を退職後、3か月以上無職だと「活動を継続していない」と見なされるため、在留期限取消の可能性があります。転職活動期間が長く続くと、次の更新審査で不利になります(新しい雇用契約書を提出する前に前職の離職日を確認する)。資格外活動許可がない状態でアルバイトをしないようにしてください。
空白期間(留学生)のリスク
留学生の場合、卒業後は在留期限までに進学、または就職活動(特定活動)ビザへ変更しなければ、その期限を経過すると不法滞在とみなされます。学生アルバイトの資格外活動許可は卒業と同時に無効となります。卒業証明書と在留期限を必ず確認し、特定活動(就職活動)への変更手続きを完了していなければ、採用は見送るべきです。
2. 業務内容の不適合リスク(技人国)
技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザの場合、転職先の業務内容が、外国人の持つ「専門性」(学歴・職歴)を欠くと判断されると、ビザが不許可となり、日本での就労ができなくなります。採用企業は、新しい業務内容が専門的・技術的な性質を持ち、かつ在留資格の要件に厳格に適合しているかを、申請書類作成時に徹底して確認しなければなりません。
3. 前職での義務不履行のリスク
特定技能や技人国人材が転職する場合、前職の企業での在留資格上の義務不履行(税金や社会保険料の未払い、不適正な活動など)が審査で明らかになると、新しい在留資格の申請が不許可となる可能性があります。企業は採用時に、前職での就労状況や生活状況について、可能な範囲で書類確認やヒアリングを行い、問題がないかを慎重にチェックする必要があります。
※在留資格「留学生」に関する過去掲載コラムも是非、チェックしましょう!
長く定着してもらうには
外国人材に長期的に活躍してもらうためには、在留資格の要件を満たすだけでなく、受け入れ企業側の体制と企業文化の醸成が不可欠です。
1. 賃金・待遇の「日本人同等以上」の徹底
在留資格の要件である「日本人と同等以上」の待遇を満たすのは最低限のルールです。定着を促すには、さらに一歩踏み込んだ公平性を追求しましょう。
公平な評価制度の整備:
給与、昇進、賞与、そして福利厚生において、日本人社員と比べて不利な条件になっていないかを常にチェックし、公平で透明性の高い評価制度を運用することが定着の基本です。
2. メンター制度と母国語支援で不安を解消
言葉の壁や生活習慣の違いからくるストレスは、転職の大きな原因です。孤独感を解消する支援が重要になります。
母国語でのサポート体制:
母国語での相談窓口や、同じ言語・文化を理解するメンター(先輩社員)を配置し、気軽に相談できる環境を作ります。
定期的かつ丁寧なヒアリング:
仕事の悩みだけでなく、生活面の不安や人間関係についても定期的な面談で丁寧にヒアリングし、孤立を防ぎましょう。
3. キャリアパスの提示と技能向上の支援
就労不可。観光や商用(短期商用)目的であり、原則として一切の就労(アルバイト含む)は認められていません。
「この会社で将来のキャリアが描ける」という確信を持ってもらうことが、高い定着率につながります。
研修制度の充実:
技能習得のためのOJTや研修制度を充実させ、個人のスキルアップを積極的に支援します。
具体的なステップアップの提示:
特定技能2号への移行や、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更など、社内での将来的なキャリアパスを具体的に提示し、長期的なモチベーションを維持させます。
まとめ
深刻な人手不足が続く日本において、外国籍人材は不可欠な戦力です。採用を成功させ、戦力として長期定着してもらうためには、企業側が在留資格ごとの転職ルールを正確に理解し、コンプライアンスを徹底することが絶対的な前提となります。
しかし、優秀な外国籍人材を定着させる最終的な鍵は、法的な要件を満たすだけでなく、彼らのキャリアを真剣に考え、育成と支援を行う姿勢です。日本人と同等以上の賃金・待遇を保証し、母国語でのメンター制度や具体的なキャリアパスを提示することで、「この会社で長く働きたい」というモチベーションを引き出せます。リスクを管理し、安心して働ける環境を整えることこそが、持続可能な外国人材採用の成功に繋がります。
KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア諸国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。
《KosaidoGlobalの強み》
1,全国47都道府県すべての企業に対応
2,介護、外食、宿泊…多岐にわたる業界で取引実績あり
3,現地で人材を教育してから入社をさせるため即戦力として期待できる
外国籍人材の採用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
KosaidoGlobalのサービスに関するご相談は、こちらからお気軽にお問い合わせください。




