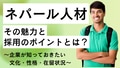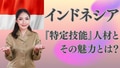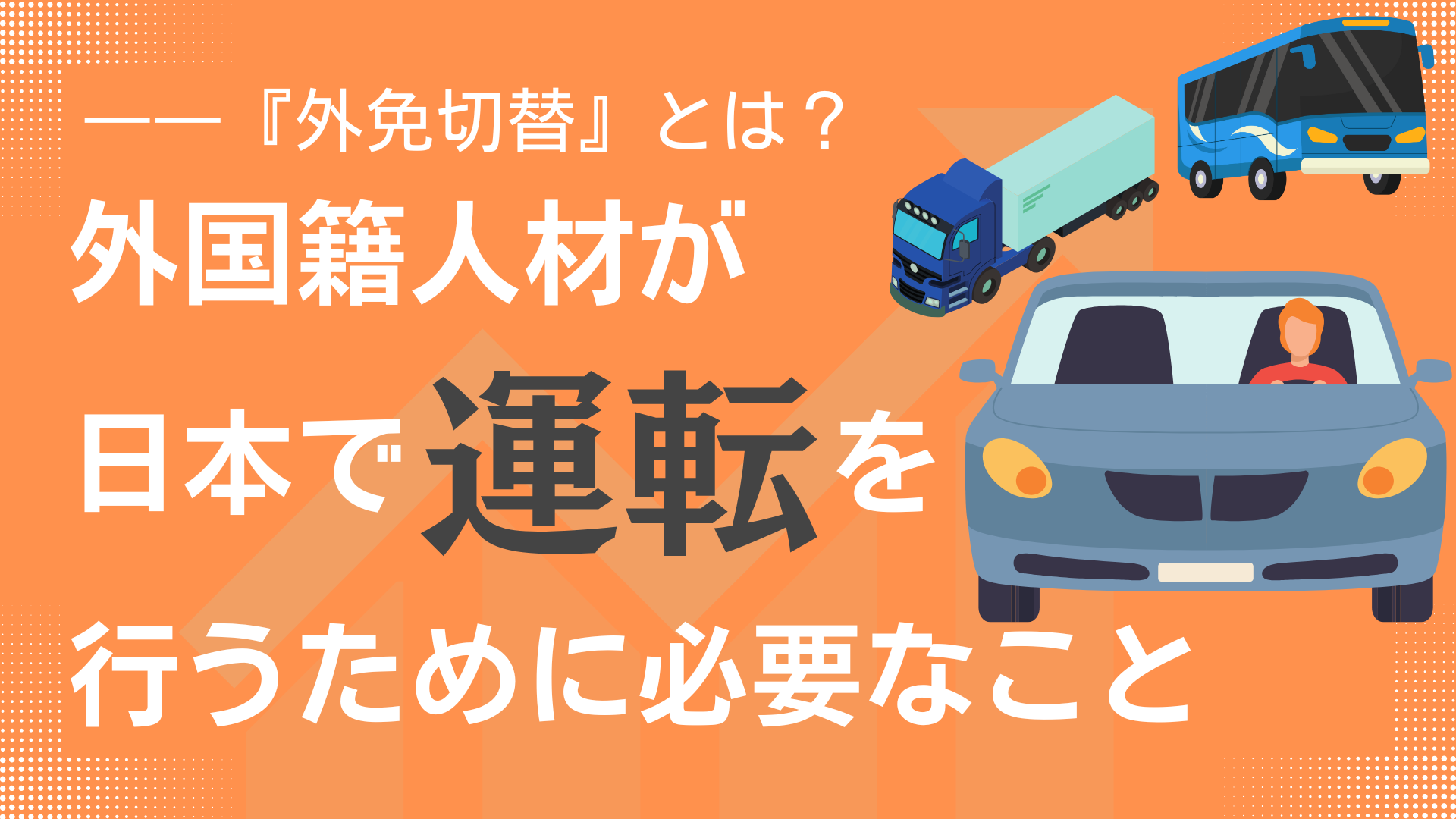
『外免切替』とは?外国籍人材が日本で運転を行うために必要なこと
特定技能で外国籍人材の受け入れが可能となった分野のひとつが「自動車運送業」です。外国籍人材がバス、タクシー、トラックといった事業用自動車のドライバーとして就業することが可能となりました。2024年12月から制度の運用が開始され、2025年に入ると全国各地の企業が本格的に導入を進めていることが度々ニュースとして取り上げられています。
そのような背景から、本記事では、外国籍人材の運転免許取得について取り上げます。外国籍人材が日本で運転を行うためには何をすべきなのか、詳しく解説していきます。
日本で運転を行うためには
日本国内で車の運転を行うためには、下記【1】【2】のいずれかの免許を保有している必要があります。
【1】日本の運転免許証
【2】国際運転免許証
※道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づくもの
国際運転免許にはジュネーブ条約に基づいて発行されるものとウィーン条約に基づく様式で発行されるものがありますが、日本で認められているのはジュネーブ条約に基づく免許です。
日本の運転免許を持っていない場合でも、国際運転免許を所持していれば、日本国内での運転が可能となります。ただし、国際運転免許の有効期限は日本への上陸日から1年間、または外国の運転免許証の有効期限のいずれか短い方が適用されるため、長期滞在の場合は注意が必要です。
また、一部地域と国では、国際運転免許証の制度が存在しません。その場合、自国の運転免許であっても例外的に日本での運転が認められるケースもあります。有効期限は国際運転免許と同じです。
外国籍人材が日本の免許を取得するためには
母国で運転免許を取得していない場合
母国で運転免許を取得したことがない場合、日本で新規に免許を新取得する必要があります。日本人が免許を取得するのと同じく、運転免許試験の適性検査・技能試験(実技)・学科試験(筆記)全てに合格し、日本の運転免許を取得することで、日本での運転が可能となります。
自動車教習所での教習の受講は必須ではありませんが、技能試験の練習を独学で行うことは難しく、練習場所の確保も非常に困難です。そのため、多くの場合、自動車教習所での教習を受講し、教習所内で技能試験を受験します。運転免許試験場では、適性検査と学科試験を受験するといった流れが一般的です。教習について受講する場合、運転免許の取得にかかる費用は、平均的に30万円ほどとされています。
【通学】と【教習所】
教習については、「自動車学校に通学する」か、または「合宿所で受講する」か、二つの選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットは下記のようになっています。
【通学】
《メリット》
教習時間を自由に組めるので、生活サイクルやその他予定と調節しながら受講することができる。
《デメリット》
時期によっては、受講予約が取りづらい場合もあるため、運転免許取得までの日数が合宿所での受講と比較して長期となる可能性がある。特に3月や8月など、学生が休暇に入る時期は混雑する。
【合宿所】
《メリット》
最短で、約2週間での運転免許の取得が可能となっており、急ぎ免許が必要な場合などは適している。また、金額についても、教習所に通う場合よりも低価格に設定されている場合が多い。
《デメリット》
合宿所で宿泊しながら受講するため、ある程度まとまった日数での予定の空きが必要となる。
運転免許を新規で取得する場合は、ある程度のまとまった日数が必要となります。そのため、まとまった休暇を取ることが可能であるか、取得希望日までの残日数等、様々な側面を考慮し、教習所の方式を選定する必要があります。
学科試験は母国語でも受験可能
日本での運転免許取得に必要な学科試験(筆記)は外国語での受験が可能です。第一種、第二種、仮免許試験対応言語は下記20言語です。
英語、スペイン語、ペルシャ語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、タイ語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、クメール語、ネパール語、ミャンマー語、モンゴル語、ウクライナ語、シンハラ語、ウルドゥー語、アラビア語、ヒンディー語
外面切り替えに伴う知識確認問題では、上記20か国に加えて、フランス語、トルコ語、ベンガル語、マレーシア語の計24か国での受験が可能です。
各免許種別・受験する言語によって、受験可能日や受験会場(各運転免許試験場)が異なるため、注意が必要です。
母国の運転免許証を保有している場合
既に運転免許を母国で取得している場合には、日本の運転免許への切り替えを行うことで、日本での運転が可能となります。これを通称『外免切替』と呼びます。(詳細については、次の段落で触れます)
取得をするための条件
上記の選択肢いずれの場合も、下記記載の資格条件【1】~【5】を満たしている必要があります。
【1】18歳以上(普通二輪は16歳以上、中型免許は20歳以上、大型免許は21歳以上)
【2】外国等で運転免許を取得後、その国等に通算して3か月以上滞在していた方
【3】普通及び二輪免許は、視力が両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上であること。一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること
【4】準中型免許、中型免許、大型免許は、視力が両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上であること、かつ、三桿法の奥行知覚検査器により3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること
【5】過去に日本の運転免許を取得していた方で、取消処分等(初心取消を除く。)を受けた方は、受験前1年以内に取消処分者講習を受講し、かつ、欠格期間経過後でなければ受験できません
外免切替について
母国等、日本以外の国や地域で自動車運転免許を既に取得しており、それらが有効な免許である場合、日本で新規に免許を取得せずとも、免許の切り替えを行うだけで、日本での運転が可能となります。ただし、取得した外国運転免許証の期限が切れている場合は申請ができません。
外免切替を行う免許センターは基本的に混みあっているため、予約してから実際に申請を行えるまで1か月以上かかる場合もあります。そのため、事前に外国運転免許証の有効期限を確認し、余裕をもって申請の予約を行う必要があります。
手順
外免切替に必要な手順を説明します。
【1】 審査の予約(免許センター)
▼
【2】 書類の提出、確認
▼
【3】 適性検査
▼
【4】 知識確認(※日本語以外でも受験可能)
(※対応言語は現在24言語であり、“外国籍人材が日本の免許を取得するためには”の“母国で運転免許を取得していない場合“内に詳細国籍を記載しております。)
▼
【5】 技能確認(※予約2か月以上待ちの場合あり)
▼
【6】 免許証交付
下記記載の一部の国と地域での運転免許を保有している場合は、技能確認と知識確認が免除されます。
【技能確認と知識確認が免除される国】
アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国(オハイオ州、オレゴン州、コロラド州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
※技能確認のみが免除されるのは、アメリカ合衆国です(インディアナ州に限る)。
外免切替に必要な書類
下記共通して提示、または提出が必要な書類について明記します。
【1】有効期間内の外国の運転免許証
【2】上記提示する外国の運転免許証の日本語翻訳文(JAFや在日大使館が発行したもの)
【3】運転免許を取得した国などに、運転免許を取得後、通算して3か月以上滞在していたことが確認できるもの(パスポート等)
【4】申請用写真
【5】本籍(国籍)が記載された住民票の写し(日本国内在住の方)
【6】旅券等(日本国外在住の方)
上記以外にも、外国運転免許を取得した国や取得状況によって、追加で必要な書類が異なります。そのため、警視庁HPに掲載されている必要書類一覧を確認し、確認する必要があります。
外免切替にかかる費用
切り替えにかかる費用は地域によって、変動しますが、2025年9月時点、東京都での外免切替費用は下記となっています。
・普通 2,500円
・原付 1,600円
・大型・中型・準中型 3,900円
・その他 2,800円
・交付手数料 2,350円
・併記手数料 200円
免許センターでは、地域によってはクレジットカードや電子マネーを利用できない場合があるため、現金を用意しておくと安心です。
制度の厳格化 ※2025年10月追記
2025年10月1日から外免切替は改正道路交通法施行規則に基づき厳格化されました。
これまでは「一時的な滞在場所を居住地として手続きが可能」「知識確認問題が簡単すぎる」といった制度の不備が指摘されていました。実際に、日本の基本的な交通ルールを理解しないまま免許を取得した外国人による交通事故も発生しており、今回の厳格化は、不正な免許取得を防ぎ、安全な交通環境を確保することが目的です。
1. 居住確認の厳格化
(免許取得時)
<これまで>
・住民票がある場合…住民票の写し
・住民票がない場合…旅券と「一時滞在証明」
<今後>
・申請者の国籍にかかわらず住民票の添付を原則化
・観光等の短期滞在の在留資格者は免許を取得できなくなる
(運転免許証更新時)
<これまで>
運転免許証
<今後>
在留カード、特別永住者証明書、住民票の写し等の掲示を求める
2. 知識確認・技能確認の厳格化
(知識確認)
<これまで>
・イラスト問題10問
・審査基準70%以上
<今後>
・イラスト問題を廃止
・問題数を50問に増加
・審査基準を新規取得時と同様の90%以上に引き上げ
(技能確認)
<これまで>
・場内実車確認
・審査基準70%以上
<今後>
横断歩道等の課題を追加し、合図不履行や右左折方法違反等の採点を新規取得時と同様に厳格化。
※外免切替する人材も多い?日本と交通ルールが似ている国を調査
特定技能「自動車運送業」で就労する場合に必要な運転免許とは
特定技能「自動車運送業」では取得条件に日本の運転免許証の保有が必須とされており、国際免許では対応できません。また、運転する車種によって、取得するべき日本の運転免許も変わり、特定技能の在留資格申請前に取得しておく必要があるため、注意が必要です。
例)トラック:第一種運転免許、準中型免許、中型免許、大型免許
バス・タクシー:第二種運転免許
トラックの場合:第一種運転免許、準中型免許、中型免許、大型免許
トラックの運転するためには、車両の種類や重量に応じた運転免許が必要になります。
普通免許:
軽トラックや1t未満のトラック
準中型免許:
最大積載量が2t以上4t未満のトラック(物流業界での需要が高まっている免許)
中型免許:
最大積載量が4tまでのトラック(配送業・建設業で求められることが多い免除)
大型免許:
8t以上のトラックやトレーラーを運転可能(長距離輸送業務等でかかせない免許)
バス・タクシーの場合:第二種運転免許
バスやタクシー等の旅客自動車を営利目的で運転するためには、第二種運送免許が必要となります。第一種運転免許を保有している場合でも、第二種運転免許を保有していなければ、旅客運送はできません。第二種運転免許を取得するためには下記条件を満たす必要があります。
【1】第一種運転免許を取得してから3年以上経過していること
※海外での運転免許取得後に現地で運転経験がある方は、運転経歴証明書などを用意することで、その期間を「運転経験3年以上」のカウントに含めることができます。
【2】満21歳以上であること
【3】適性試験、学科試験、実技試験、すべてに合格すること
なお、受験資格特例教習を受講することで『運転経験1年以上かつ19歳以上』に条件を引き下げることも可能です。
※特定技能「自動車運送業」については、下記コラムで詳しく解説しております。
まとめ
外国籍人材が長期で運転する必要がある場合は、日本の運転免許が必ず必要となります。日本の免許を取得するために『外免切替』を行う場合、必須書類等や手順に注意が必要です。
また、特定技能「自動車運送業」での就労を希望する場合は、在留資格申請までに、業務内容に合わせた日本の各種運転免許が必須となりますので、事前にしっかりと準備をしておきましょう。
KosaidoGlobalは東証プライム上場企業である広済堂グループが提供する、外国人労働者の人材紹介サービス・登録支援機関です。アジア諸国の送り出し機関と提携し、日本国内の企業様に「特定技能」「技人国」を中心とした優秀な人材をご紹介するとともに、人材の活躍や定着に向けた手厚いフォローも提供します。
《KosaidoGlobalの強み》
1,全国47都道府県すべての企業に対応
2,介護、外食、宿泊…多岐にわたる業界で取引実績あり
3,現地で人材を教育してから入社をさせるため即戦力として期待できる
外国籍人材の採用をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。

日本の交通ルールに素早く順応!
即戦力スリランカ人ドライバー採用
採用から定着までワンストップでサポート。東証プライムグループがお届けする安心サービスです。